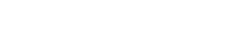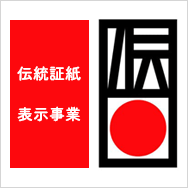又吉恭平

西表島といえば「イリオモテヤマネコ」「カンムリワシ」などに代表される独自の生態系や、「マリユドゥの滝」や「浦内川」など多くの自然が残る島として知られている。人が住む場所よりも森林が占める割合が多いこの島は、いまだ未知の部分も多く、魅力に満ちている。
そんな島で三線店を営む職人がいると聞いた。私は那覇空港から石垣島に飛んで石垣港へと向かい、そこから船に乗り、さらにバスに乗り換え目的の場所を目指した。その場所は西表の西側の「上原」集落にある。しかし、目的地に近づいているはずだがバスの通る道の左右には建物が殆ど建っていない。この道で大丈夫かなと思うが、バスは構わず進んでいく。すると、右側に「唐変木」という看板を発見した。そして傾いてはいるが「さんしん屋」の看板が目に留まった。バスを下車し、矢印の示す方向に進む。 そこは草木の生い茂った道があった。その道をさらに進むと「唐変木」という瓦屋根の建物があった。しかしここが三線屋というわけではなさそうだ。
そこは草木の生い茂った道があった。その道をさらに進むと「唐変木」という瓦屋根の建物があった。しかしここが三線屋というわけではなさそうだ。
先に進むと、特に何の看板も無い倉庫のような場所にたどり着いた。思い切って中に入ってみた。そこにはいくつもの木材、そして三線の棹が置かれていた。奥の扉からは灯りが漏れている。さらに進むと、そこには小さな作業場があり、棹へ塗りを施している人物がいた。
その人こそ今回の主人公、奥田武氏(以下敬称略)である。
熊野から沖縄へ
奥田武は昭和18(1943)年生まれの74歳である。出身地は三重県の熊野、「熊野古道」で有名な地域だ。幼少期の奥田は熊野の雄大な大自然の中、元気いっぱいに育った「勉強ばせんと遊んでばっかりおった」。熊野の言葉遣いで幼少期を振り返りながら笑う。奥田は15歳から大工見習として働きはじめた。「昔の丁稚奉公。大工の弟子に入って、5年間修業して、それからずっと大工」。熊野では木造建築が一般的だったため、奥田は特に木を扱うことを得意とするようになる。
そんな奥田が沖縄へ越してきたのは1972年。沖縄が本土復帰を迎える年だった。「復帰の1年前に一度、視察ゆうたらおかしいけど、来て。ほいで復帰前はパスポート持ってきたんだよね」。沖縄が新たな時代へと踏み出す激動の時期であった。
奥田がまず居を構えたのは宜野湾市大山。この地に住みながら、沖縄のいたるところで建築の仕事に携わった。とにかく毎日働く、そんな日々が約10年続いた。しかし、あまりにも仕事で忙しい日々をおくっていた奥田は途中で体調を崩しまう。それがきっかけとなって、奥田は西表で暮らすことを考えるようになった。実は老後を西表で暮らすつもりで土地買っていたのだ。
そして西表へ
奥田は念願の西表に引っ越して来た。土地はすでに購入していたが、まだ住む家はない状況。そこでまず干立(ほしたて)集落に仮の居を構え、買った土地に家を建て始めた。仕事をしながら、空いた時間を利用しての家作りだった。そして数年の時を経て家は完成した。奥田の西表での物作りはここからはじまった。ちなみに現在の住まいの横に併設されている「唐変木」という店舗も、奥田が一から作った建物で、自宅が完成した後、数年の歳月をかけ作り上げた。現在は奥田の妻が飲食店を経営しており、カレーやコーヒーを楽しむことができる。

唐変木
三線作りのきっかけ
奥田が三線作りに取り組むようになったのは約20年前。友人の宮良用範が八重山古典民謡の教師免許を取得したのを記念して、自身が作った三線をプレゼントしたことがきっかけとなった。「それまで三線は遊びでは作ってたけど、記念に作ってあげたやつはけっこう調子がよくて」。奥田はその持ち前の器用さから、特に他の職人から指導を受けることなく本格的に三線を作りはじめた。「友人の又吉真三さんが書いた図面を見て作ったよ。一応俺大工だからよ。図面みたらわかる」。そんな奥田が唯一習ったと言うのは「皮張り」。皮張りに関しては那覇市若狭にあった金城三線店の指導を受けた。
また奥田はこれまで三線の全ての7つの型を作成し、過去の名器「志多伯開鐘)」や「西平開鐘」の製作にも取り組んだ。前述した「唐変木」には奥田自らが製作した7つの型の三線が展示されている。

木工芸の技術を三線に活かす
奥田は、木工芸の職人という一面も持つ。10代の頃 から大工として木材を扱っていたこともあって、ひとり立ちした時から、お椀などの食器なども手がけるようになっていた。
から大工として木材を扱っていたこともあって、ひとり立ちした時から、お椀などの食器なども手がけるようになっていた。
木工芸はまず木を彫り、形を整える。その後、漆を塗る。「漆ってのは色んな塗り方があるけど、自分は擦り漆(すりうるし)で塗る。塗ってはふき取り、塗ってはふき取り、それを30回くらい繰り返す」。聞いているだけで気の遠くなる作業だが、奥田は妥協することなく塗りを繰り返す。奥田が見せてくれたのは大皿やお盆。ここにも漆が丁寧に塗られている。
さらに奥田は一本の三線を取り出した。その三線を見て驚いた。棹が朱色なのだ。「朱殷(しゅあん)ていう色。普通は真っ黒さね、みんな。だけど俺は真っ黒で消してしまうのが嫌だから、摺り漆にしとるんだ。これなんかよく見ると模様が綺麗だよ。木目が綺麗に出とるだろ」。確かに奥田の作る三線はどれも木目がはっきりと現れており、美しい。木工を製作することで磨かれた美的感覚は、三線作りにも大いに活かされているといえよう。
個性あふれる作品
奥田は、三線作りの殆どの工程を自身でこなす。棹の作成はもちろんだが、チーガもチャーギ(イヌマキ)の木を材料に一から作る。カラクイ(糸巻)も作る。「ただティーガー(胴巻き)だけはできなかったさ」と笑う奥田。
そんな奥田の作る三線の中には他ではあまり見ない独自の作品がある。「つなぎ三線」という、三線は棹を3つに分解することが可能な楽器で、旅行に持っていくのに便利である。このつなぎ三線は、又吉真三が持っていた楽器を参考にして作成したという。県外や海外から訪れた人が店頭で見て購入したそうだ。

つなぎ三線
そして奥田の作る三線の最大の特徴は、奥田オリジナルのカラクイ(糸巻き)にある。奥田のカラクイは素材の木目を活かすため、色は塗らずそのままに作られている。通常の三線につけられるカラクイは普通、三線とほぼ同じ色に塗られているが、奥田のカラクイの場合、その色は茶色で、棹とカラクイの区別がはっきりとしている。そのことにより、棹の形や色合いがはっきりとわかり、美しさがより強調されて見える。「俺はもう、人と同じいう言葉、ものすごく嫌なわけ。だから人とおんなじカラクイを使いたくないわけ」。奥田独自のカラクイは職人としてのプライドが現われたものといっていいだろう。
カラクイ
普段みることができないチーガ(胴)の内部にも工夫がある。通常の三線の胴内は滑らかな円形となっている。しかし奥田のチーガでは、その中身で凹凸になっている部分がある。実はこの凹凸、三線の名器と称される「開鐘」のチーガにも同様の工夫がみられる。

チーガ
チーガは三線の音質に大きく影響する重要な部分で、この凹凸は音質の向上を狙った工夫といえよう。音楽ホールで生音を増幅させるために使用される「反響版」のような役割を果たしていると考えられる。実際に弾いてみると、程よい余韻があり、琉球古典音楽や八重山古典民謡の発声にちょうど適した音質であるように感じられた。このチーガの工夫も、ほとんど全ての部位を製作する奥田だからこそできる工夫だ。

三線作りについて
奥田にとって三線は、どんな存在なのだろうか。
「三線は難しいよね。楽器だから。ほいで音色も好みがあるからよ」。三線作りの難しさは見た目だけでなく、楽器としての「音」も表現しなければならないことにある。強い言い方だが、どんなに見た目が美しくとも、音が良くなければ楽器としての価値は半減してしまう。三線職人は美的センスと、確かな音感の双方を兼ね備えることが必要なのだ。
また奥田は三線の素材となる「木」についても、「木というのは生き物だもん。特に八重山クルチの場合木取が難しい。変なとり方するとね、曲がったりひねったりすることもある。素材を知ることが一番大事や」。15歳の頃から木材を扱ってきた奥田にとっても、三線の素材は容易に扱えるものではないことがわかる。
「三線つくりはきりがないよね。自分ではこれが100パーセント言うのはひとつもない。やればやるほど難しいさ」。
西表で三線を作る意味
奥田はなぜこの西表の地で三線を作るのだろうか。
「三線作りは楽しくやっとるよ。お客さんはあんまりこないけど、その分一本一本丁寧に作ってる。那覇とかだったら漆を何回も塗る時間はないはずだし」。
西表では時間に追われることなく作品づくりに取り組めるのが、何よりの良さであるという奥田。三線一本にかける時間は長いが、その分、じっくりと丁寧に作られる楽器はどれも美しく魅力に溢れている。

自然と共に生きる
西表では猪を食する。猪は毎年11月15日から2月15日までの3ヶ月間、猟が解禁となる。取材を行った時期はちょうど猟のシーズンであった。「しかけた罠を見に行こう」そう言って山へと案内してくれた。奥田は急な道も難なく進んでいく。その後、いくつか罠を仕掛けた場所を案内してもらったが、残念ながら今回、収穫はなかった。だが奥田の職人としての表情とはまた違った一面を目の当たりにできたことは私にとって大きな収穫となった。都会に住んでいては得られない日々自然と触れ合う経験は、奥田の三線作りに何らかの影響を与えているのではないか、そんな気がした。