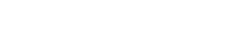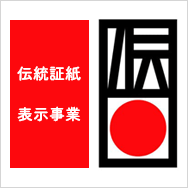むらさき

2月初旬、三線組合を訪れると、そこに展示されている作品の中で、ひときわ異彩を放つ三線が私の目に飛び込んできた。
全身がむらさき色の三線。
棹だけでなく、胴の蛇皮やティーガーの生地までもむらさき色というこだわりぶりである。
その名も「ムラサキツギハギ三線」。
作者は沖縄にルーツを持つ日系4世の志良堂サユリさん(以下敬称略)。ブラジル出身の27歳である。現在、ウチナーンチュ子弟等留学で来沖し、那覇市の尚工房で岸本尚登さんから三線作りを学んでいる。
明るくはつらつとした人柄。取材の日は、直前まで取り組んでいた三線の胴の皮張り作業を中断してインタビューに応じて下さった。冬の寒さをものともしない、エネルギーに満ちあふれた方だ。
志良堂のルーツ
志良堂は沖縄本島北部・本部町出身の曽祖父を持つ。曽祖父は約100年前にブラジルへ移民。志良堂には、その曽祖父の思い出が今も脳裏に残っている。
「私、子どもの時ね。でも、ひいおじいちゃんはウチナーグチだけしゃべりましたから、(私とは)全然しゃべりはできなかった」。
祖父母はブラジルで生まれ育ったので、孫たちとはポルトガル語で話したが、沖縄の生活文化に関しては曽祖父の影響があって、その影響を色濃く受け継いでいた。
「オバ―の所、まだ仏壇あるし。そう、大きい仏壇ね。沖縄の仏壇」。
そのような環境で育った志良堂。子供の頃は県人会のグシケン先生やシマダ先生から三線を教わった。また、県人会でもエイサーや琉舞を踊るなど、積極的に沖縄の芸能文化に親しんでいた。その頃、沖縄へ行った祖父からあるお土産をもらう。
三線作りのきっかけ
「(祖父は)1か月か2か月ぐらいこっち(沖縄)に来て、遊ぶだけは…ちょっとつまらない。何するね? じゃあ、三線を学ぶね! と言ってた」。
今から15年ほど前、沖縄で三線の作り方を学んだ祖父。
「オジ―はすごかったよ。これを見て(胡弓を指さす)、見るだけで作れる。すごかった。三線もね、1か月だけ学んでブラジルに」。
祖父は自作の三線を孫たちに与え、その後もブラジルで三線などの楽器を作り続けた。そして、孫たちに沖縄の音楽や文化への興味を抱かせた。
「オジ―がね、三線作ってあげて。で、音楽とか三線を勉強して、と(孫たちに)言ってた」。
研修生として沖縄へ
2015年、大学生の志良堂は、南米本部町出身指定研修生として沖縄へ渡り、初めて”ふるさと”の地へ足を踏み入れた。しかし、沖縄に滞在中は名桜大学に通い、留学生センターに住んでいたため、地元の人々と話す機会は少なかった。その中で、カナダから留学に来ていたブライアンさんと知り合う。
「ブライアンはこっちに来て、三線作りを勉強してたね。ブライアンに会って、あー! 私も三線作りを勉強したいと思って、ブラジルに帰って、日本語を一生懸命勉強して、県費(ウチナーンチュ子弟等留学事業)で来た」。
ブライアンとの出会いによって、ウチナーンチュ子弟等留学事業で三線作りを学ぶことができることを知った志良堂は、名桜での留学を終え、ブラジルに帰国するとすぐに新たな留学制度を利用するため取り組んだ。無事審査に合格。2017年7月、再び来沖した志良堂は、尚工房の門をたたき、岸本のもとで三線作りを学んでいる。
7か月で23挺
「今、(三線が)20挺。あと、六弦1挺と、胡弓は2つ」。
この留学の約7か月の間に23挺を作りあげた志良堂。現在も新たな三線の製作に取り組んでいる。棹材に図面を写すことから、岸本は丁寧に教えてくれるという。
「ゆっくりで教えてくれる。いつもね、ちょっとだけやって『先生、大丈夫ですか?』って見せると、『じゃあ、こっちはもっと削って』とか。優しい、先生」。
嬉しそうに語る志良堂の笑顔から、岸本への信頼がうかがえる。
「(1挺を作るのに)最初は3週間ぐらい。でも、全部手で作ったね、最初は。今はちょっと機械が。先生は全部手で教えて、この機会が(ブラジルに)なかったら、これでして、って。3週間ぐらいかけた。今は1週間かな? もっと早いかな?」
岸本は昔ながらの三線製作方法と、機械を用いた今の方法を両方教えた。
「先生は昔のやり方も全部教えたね。で、さゆりはできるかな? できないかな? と考えて、新しい作り方を教えてる。私もね、女の子だから力がない。時々は、たとえばね、この下(爪裏と呼ばれる、棹と胴の結合部分)にノミで削るね。でも、硬い木は、もうできないこともあるから機械で、これで削ってとか」。
沖縄に来て毎日、三線作りに励む志良堂だが、まだ理想の形には到達できていない。特に、三線の顔とも言える「天」の下の部分や、曲線を描く鳩胸(棹の中心より下、胴の接合部分にかけてゆるやかなふくらみを描く部分)が難しいという。岸本の三線と比べながら、「先生の三線のようにきれいに作れるようになりたい」と抱負を語った。

失敗しなさい
岸本の教えは「失敗しなさい」。失敗も自分でやってみない限りはわからないという岸本の思いがそこにある。
いろいろな木材で三線を作ってみるのも、岸本のチャレンジ精神からきているのだろう。
「クヮーギとか、パープルハート、黒木、白い黒木(まだ若く、白い部分が多い黒木)…。これは、こっちで作って、ブラジルに帰ったら、あっちの材料はどれに似てるかわかる。そのために色んな材料で作ってる」。
そうした中で生まれたのが、「ムラサキツギハギ三線」。中米から南米北部にかけて分布しているパープルハートを用いて作った。木材はまっすぐな状態で、三線を作るには幅が足りなかったため、「天」の両サイドは付け足して作った。だから「ツギハギ」三線。ユニークで、見る者の目を奪う作品だ。
この三線は、第40回沖縄伝統工芸公募展で新人賞を受賞した。もしこの三線を売るとしたら、どんな人に使って欲しいか聞くと、
「沖縄の文化を伝えたい人」。
志良堂自身も、沖縄のことをもっと多くの人に知って欲しいと考えている。
沖縄の心
「沖縄の人はいつも頑張りますね。それも、戦争あったね、こっち。でも、みんな頑張ってる。 “had bad things, but keep smiling”(辛いことがあったのに、笑顔を絶やさない)」。
かつてのウチナーンチュが経験した海外移民や戦争の歴史を、志良堂は三線を通じて伝えていきたいという。
「オジ―はいつも話していた。昔の…ひいおじいちゃんは移民したね。でも、その時はとっても大変だった。もう沖縄帰りたいけど、お金もないし、仕事しないといけないし。でも、あっち(ブラジル)で沖縄の文化とか伝えたね、私まで。オジ―とかお母さんは沖縄の文化、沖縄の心みたいのを。文化じゃなくてひとの心とか、これを伝えたから、私も伝えたいと思って。
でも、どうやってこれをする? と考えたね。私は(三線を)弾くのはあまり上手じゃないから、じゃあ三線作ろうと思った。手作りが好きだから」。
祖父や母から伝えられた「沖縄の心」を他の人にも伝えたい。志良堂にとってその方法は、祖父と同じく、三線を作ることだった。
「オジ―は、これ(三線)は作ってみんなあげて、言葉は遣わないね。三線、『これを勉強して』、『これは大切なもの』とか、言葉は遣わない。でも気持ちは伝えたから。私もこんな感じでなりたい」。
言葉にできない文化や心を孫たちに伝えた祖父。
「みんなから好かれる人だった」。
ムラサキツギハギ三線で新人賞を受賞したという知らせを受けたその日、志良堂は祖父の訃報に接した。
「同じ日に、夜は妹と電話をして、『オジ―が亡くなった』って。もう、こっちでいっぱい頑張って(作った三線を)オジ―に見せたいと思って。でも、できない」。
続けて…
「でも、見たと思う…。見たと思う。写真、いっぱい送って…」と、志良堂は少しさみしそうに笑った。
ブラジルに戻ったら…

ブラジルに戻っても三線を作りたい! と目を輝かせる志良堂。
志良堂が作った作品をよく見ると、カラクイ(糸巻き)やウマなどの小さな部分に、緑・青・黄色のブラジル国旗の色が施されていた。志良堂の三線は、ブラジルと沖縄の心をつなぐ架け橋となって、広がっていくことだろう。
最後に、ブラジルに戻ったらまず何をしたいか尋ねると、明るい笑顔でこう答えた。
「オバ―の家に行く。仏壇に、三線見せに」。
伊良波 賢弥
沖縄県三線製作事業協同組合
支援:公益財団法人沖縄県文化振興会