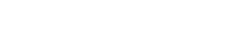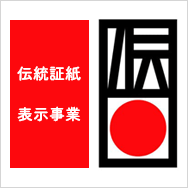伊良波 賢弥
「JICAで働いたら?」
 那覇市の尚工房。
那覇市の尚工房。
都会のせわしさを忘れさせるような静かな工房で、三線や胡弓の製作を手掛けている。物腰が柔らかな岸本尚登さん(以下敬称略)の姿は、私が抱いていた職人のイメージとは異なっていた。
自己紹介もそこそこに椅子に腰かけると、大学三年の私に対し「将来は何になるの?」と質問された。「まだ何になろうか決まっていなくて…」。今まさに進路に迷っている旨を伝えると、「JICAで働いたら?」と唐突に提案された。「私があなたの年齢だったら海外に行くけどなあ」。
何気ない問いかけであったが、岸本の取材を通して、岸本が世界を志向していることが伝わってきた。そして私自身、世界へ目を向けることの大切さをつくづくと考えさせられた。
三線職人の家に生まれる

岸本尚登は1969年11月、那覇市に生まれる。祖父、父ともに三線職人であった岸本は、物心がつく頃から三線作りに囲まれた生活環境の中、幼少期から祖父の手伝いで三線作りに関わっていた。「当時は遊び道具も今のようにないけど、(家には)機械も材料もあるから、遊び道具を作りながら、おじいに言われたことをやっていたという感じ」。
岸本の祖父は大宜味村の出身。”大宜味大工”で有名な地域だが、祖父も例外ではなく、建築業をなりわいとし、名護で生活していた。戦後、名護から那覇市松川へと移り住むが、建築業は引退して、下駄やふすまを作りながら三線作りを始めた。これが、岸本一家の三線作りのきっかけとなる。
那覇市松川には岸本の祖父と伯父、それに父が隣り合って三線工房を開いた。そのような環境で育った岸本だが、地元の工業高校を卒業した後、生まれ育った沖縄を旅立ち、三線に囲まれた生活から離れることになる。
上京して恋しくなった故郷の三線
丁度、岸本が状況して働いたのはバブル期の真っ只中。当時、東京では沖縄での収入と比べものにならないほどの給料がもらえたという。しかし、上京して4年ほどが経ち、バブルが崩壊した1991~1992年頃、岸本は故郷・沖縄へ帰ることを決めた。「ヤマト(本土)に行って、ちっちゃい頃から作っていた三線が、離れれば離れるほど余計恋しくなって・・・」。
しかし、沖繩へ帰ってはみたものの三線職人の道を決心したわけではなかった。当時の岸本は将来何をしようか、まだ進路に迷っていた。その間、家では慣れ親しんできた三線作りや、父の営む三線工房の配達を手伝うなどしていた。配達で様々な三線工房をまわり、三線職人の「先輩方」から話を聞くうち、三線作りへの興味や意欲が日に日に増していった。「先輩方」の中には岸本に三線作りの道に進むことを勧める人もいた。
「先輩方」を訪ね歩いて習う日々
「配達で行く度に、避ける人もいるけど『(三線作りを)やれ、やれ』と言う人もいた。そんな風に色々な先輩方と会いながら、やった方が良いのかねってなって・・・」。徐々に三線作りの魅力を感じ始めた岸本。師匠は父なのかと思いきや、そうではなかった。
「親子の場合は喧嘩するんですよ。あまりに身近すぎて。それよりは先輩に習いに行った方が良いと思って」。父とぶつかって工房を出ては、先輩方の工房を訪ねて研鑽を積む日々。「もう何十名の所に行ったかね。昔の先輩方は”グヮンクー(頑固)”な面があって、すぐには入れてくれない」。それでも繰り返し説得して、色々な先輩方から教えてもらった。
岸本が本格的に三線作りを始めた当時、THE BOOMの「島唄」が人気となった。その時流に乗って三線の需要は高まった。「あの時は三線が足りなくて。三線を求める方はいっぱいいたんだけど、三線を作る人が少なく、供給が全然間に合わない時代だった」。三線は作れば作るほど売れた。しかし、岸本は自分の技術が追い付いていないことを実感していた。それを補い、さらなる技術の高みを目指し、多くの先輩方の所へ習いに行った。
「物作りって面白いね。やればやるほど壁がどんどん高くなっていく」。その壁を乗り越えるのに先輩方の教えがカギとなった。
長いスパンで考えること
しかし、先輩方からの教えは、自分の技量が届かないうちは理解できない。「やっていくうちに、あのサンシンヤ―(三線職人)が言っていたことは、このことを言っていたんだねって思う。やってみない限りはわからない」。今なお理解できていない教えもあり、壁にぶつかることもしばしばあるという岸本。
三線製作も、始めて一、二年では理解できない。三線の棹ひとつをとっても、木材が時間を経る中でひねったり、割れたりしないか、何年もの期間をおいて見極める。三線職人はそれだけ息の長い仕事が必要とされる。
後継者育成に関して岸本は、三線作りは「理解するのに時間がかかる」として次のように語る。「五年、十年先を見るなら良いけど、みんな今しか見ない。だから途中で止めてしまう。あと何年か続けたらできるのにと思う」。三線に限らず、伝統工芸を受け継ぐには根気強く、「我慢」して続けることが求められるようだ。
海外に残る豊かな沖縄文化

「作品が一番の先生」と語る岸本。2011年、三線の鑑定と琉球諸語(シマクトゥバ)の収録を目的とした調査で、海外の三線鑑定に立ち会ったことがある。その時、多くの作品に出会い、それが現在の三線作りの糧になっている。それだけではない。海外へ行き、現地の県系一世や二世に会うことで学ぶことも多かった。「県人会の結束ってとてもすごい。沖縄文化を守るため、一生懸命に今でもやっている。ウチナーンチュが忘れている『ユイマール精神』や『イチャリバチョーデー』が向こうにありますから。こっち(那覇)はリトル東京になりつつありますよね」。現在でも琉球諸語をはじめ、豊かな沖縄文化が、遠い異国の地に残されていることに感銘を受けた。
「トゥバラーマ」との出会い
岸本は八重山の古典民謡を習っている。以前から歌三線を学びたいとは思っていたが、仕事の関係上、入門を先送りにせざるを得なかった。転機は、先に述べた調査で、南米諸国と米国のロサンゼルスをまわった時のことだった。ブラジルに滞在中、この調査団のメンバーで、八重山古典民謡保存会の師範・山城直吉氏が、八重山の民謡「トゥバラーマ」を弾いて歌う場面に出会ったのだ。
「そしたらとても感動して。こんなおもしろい曲があるって初めてわかった」。山城氏の「トゥバラーマ」を聞いて心打たれた岸本は、これをきっかけに山城氏から古典民謡を習い始める。
全世界で三線が親しまれる日を夢に
最後に三線職人としての理想を伺った。「私の作った三線を持っていてくれたら、それが一番嬉しい。その国に行って、私が作ったのが『ここにあったんだね~』って思えたらとっても嬉しいわけ」。
夢は三線を世界に普及させること。

「国によって材質も違うし、音色も違う。音楽のジャンルも違う。ギターは色々なジャンルに合うように開発されている。三線も弾き手がやろうと思ったらいくらでも(その国に合うように)変えられるんじゃないのかな?ハワイのウクレレが全世界で普及しているから、できないことではない」。
かつて唐(中国)や大和(日本)、真南蛮(東南アジア)など諸外国との交流を通して独自の文化を築いた琉球王国。沖縄県となった後は、多くの移民を送り出し、沖縄文化が世界へと渡っていった。このように、琉球・沖縄の歴史は他の国々との関わりとともにあった。世界を股に掛ける気風は現在の沖縄の人々(ウチナーンチュ)にも受け継がれていると思う。
世界各地で自分の作った三線に出会えることを願う岸本の夢の実現は、そう遠くないかもしれない。

沖縄県三線製作事業協同組合
支援:沖縄県、公益財団法人沖縄県文化振興会