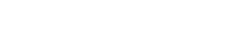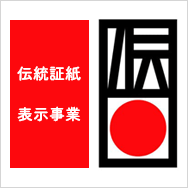世界を魅了する三線音楽
沖縄県民のみならず、日本や世界で愛好者が増えている三線音楽の島唄。
牽引する第一人者として自他ともに認めるのが、知名定男氏。島唄の三線奏者として、新唄の作詞・作曲家として、プロデューサーとして、幅広い活動は誰しもが認める第一人者である。
知名氏の三線音楽に対する想いをお伺いするとともに、知名氏の音楽の根幹をなす、三線そのものの魅力についてもお伺いした。
大阪で培われた琉球芸能
知名定男氏(以下敬称略)は、1945(昭和20)年4月21日に大阪で生を享けた。
父は戦前から三線奏者として名を馳せた知名定繁。母は澄子。
父母ともに島唄の奏者として活動しており、定男も母の教えを受け、三線を習い始めたのが5歳。「物心つく前から父や母の三線を聴いていたから、沖縄の言葉で言う、ミーナリチチナリ(見て聞いて)して育ったわけ。だから音楽の道に入ったのは早かったといえるでしょうね」。
2018年現在、定男は72歳。芸歴は67年を数えることになる。
また、定男は幼い頃から天才少年として評判を呼んでいた。そのころの天才ぶりを物語るエピソードがある。「父のお弟子さんたちの三線を聴いて、チンダミ(調弦)がおかしいって言って、なおさせたりしていたよ」とのこと。
唄・三線の音色に囲まれていた環境はもとより、持って生まれた定繁・澄子の血を感じさせる話といえよう。
芸能の道

前述したが、定男が芸の道に入ったのは5歳の頃。「そのときは、自分自身の気持ちなんてないよ。父や母にやらされていただけ。当時は大阪に県人会があって、県人の集いという集まりを持つんだけど、その時に余興で呼ばれて琉球舞踊を踊ったり三線を弾いたりするわけ。そうするとおひねりが飛んでくるさ。それが目当てだったんだろうね」。
しかし、そのように父や母の言う通りに踊りや三線を弾く日々だったが、沖縄の芸能が決して好きであったわけではない。「当時は朝鮮戦争があって、日本が戦争特需で湧いているとき。敗戦のどん底から回復しつつある時代。そんなとき、沖縄の音楽や言葉に対して差別的な言葉を掛けられることが多かったんだよ。特に学校では、いろいろ言われるからね」。
沖縄出身者の間では、天才少年として高い評判を受けていた定男だけに、いわれなき中傷を受けることも多かった。特に沖縄の芸能が好きなわけではなく、「やらされていた」と感じていた定男は「ウチナーが嫌というのが本当だった」。
仮定は禁物だが、定男が大阪ではなく、沖縄で生まれ育っていたなら、どのような道を歩んでいたのだろうか。大阪で生まれ育ち、父・定繁や母・澄子、そして普久原朝喜(三味線の名手として知られ、1927年にはマルフクレコードを設立。多くの琉球民謡を世に出している。(中略)大阪で研究所を開き、琉球芸能を広く紹介した功労者でもある。=沖縄大百科事典より)の薫陶を受けたことが、その後の定男を形作る基盤を成したともいえるだろう。それは、「何やかんや言っていても、私には沖縄の音楽が身に沁みついているわけ」という知名自身の言葉に表れているような気がする。戦後の混乱の真っただ中にある沖縄では決して味わうことのできないような大阪での生活だったともいえる。
父・定繁
定男にとって、父・定繁とはどのような人物だったのだろうか。
「父は、大阪にいるときも三線を教えていた人。影響を受けなかったといえばウソになるけど、あまり教わったという記憶はないね。今で言う放任さ。幼い頃は、母に教わることが多かったくらいだから。面倒くさいとおもっていたんじゃないかな。でも、先を見通す目はあったと思う。大阪時代から、『これからは音譜を見て演奏する時代が来る』と言っていたから」。
大阪時代、沖縄の音楽を採譜することを行い、西洋音楽との融合を図っていた父・定繁。「音譜を見て、初見で演奏する音楽家たちの姿を見ていただろうからね」。
しかし、定男にとって、その経験が大きく花開くこととなるのは、幾年か待たなければいけない。
スターダム
12歳のとき、沖縄へ。父・定繁は帰郷、定男にとっては初めての地となる沖縄であった。
しかし、平穏無事な航海ではなかった。パスポートや証明書を持たない密航であった。何とか難関を乗り越え、本格的な沖縄音楽の道を定男は歩み始めることとなった。登川誠仁の内弟子となった定男は一気にスターダムへと駆け上がっていく。ディグ音楽プロモーションのホームページから、以降の活躍ぶりを引用してみる。
’57年に父、定繁とともに沖縄へ移る。その後登川誠仁(のぼりかわせいじん)に見出され
内弟子となり、12歳の時に『スーキカンナ―』で華々しくデビュー、天才少年現る!!
と、一躍注目を浴びる。嘉手苅林昌(かでかるりんしょう)、普久原恒勇(ふくはらつね
お)、照屋林助(てるやりんすけ)など数多くの沖縄民謡黄金時代の諸先輩方から多くの
“ウチナー”を学ぶ。日本本土復帰前の’71年『うんじゅが情ど頼まりる』が空前の大ヒット
となる。その後、’78年キャニオン・レコードより『赤花』で日本本土デビュー、これに収
録された『バイバイ沖縄』は音楽界はもとより、多方面へ問題提起をした楽曲として、話題
となる。レゲエを島唄にミックスさせたこの曲は、当時のミュージシャンへも影響を与え
た。2000年6月、サミット沖縄芸能派遣団欧州公演(ロシア、フランス、イタリア)の総合
プロデュースを担当し各国で大きな評価を得る。また、沖縄サミットの県広報曲『語やび
ら』の作詞/作曲、安室奈美恵の歌った『Never End』へも三絃で参加。
しかし、定男の芸能活動は順風満帆であったわけではない。10代後半から20代前半にかけて、音楽を離れたり、西洋音楽の世界に関わっていたりもした。「19歳のころはクラシックギターを弾いたりしていたよ。でもやはり沖縄の音楽になってしまうんだな。。『踊りくはでさ』をクラシック奏法で演奏したりしてね。だから20歳か21歳のあたりから、沖縄音楽と西洋音楽の融合を考えるようになっていったわけ」。
それには「普久原恒勇さんと、照屋林助さんから受けた影響は計り知れないものがある」。大阪時代に培われた基盤と、天才少年と言われた時代に出会った師匠・登川誠仁の教え、そして今でも多大な影響を受けたという、普久原恒勇や照屋林助など、沖縄芸能史を彩る多彩な人々が、知名定男を形作ってきたといっても過言ではないのかもしれない。
そこには常に三線の姿があると考えるのは考えすぎだろうか。
師匠・登川誠仁
「三線と一心同体の人。三線を愛し、女と酒を愛し、博打を愛した人。それでありながら、教養をみせたりする不思議な人でもあったな」。
三線との関わり
定男が三線を手にしたのは、5歳の頃。「そのときは親父の三線を借りただけ。その後、沖縄で登川誠仁の内弟子時代、久葉の骨と言われるもので、12歳から内弟子を卒業するまで3年間使ったな」。他には今でも家宝として大事にしている三線を、大阪から持ってきている(この三線に関しては後述)。「あまり三線を買ったという記憶はないよ。正直にいえば、5年前に初めて購入した」とのこと。
そこで定男に、三線の魅力について聞いてみた。
「三線の音色を聴くと、自分自身の観念がふくらむという感じがする。沖縄や三線そのもの、そして自分自身の持つ歴史や重み、愛や怨念といったものまで感じることができるわけ。それを特に最近、深く感じるようになった」という。また。「三線は、代々受け継がれてきたものも多い。その価値観がわかるようになったのは30代に入ってからかな」。ちょうど、「赤花」で日本デビューを果たした時期と重なる。やはり、三線そのものが持つ魅力(定男はそれを価値観と言っているように思える)を体感し始めた時期であり、その魅力があったからこそ、沖縄音楽をさまざまなジャンルと融合し、人々へ伝えたいと思い始めた時期なのであろう。
また、これまでに使ってきた三線は10挺程。同じように見える三線でも、それぞれに手触りが異なるし、フィットする感覚が異なる。「いくつか並んでいても、結局は同じ三線に手が伸びているんだよね。それは理屈では言い表せない。なんとなくしっくりくるという感覚」なのだという。それでもあえて聞くと、「絃の強弱や重さなのかもしれない。やはり自分の感覚としか言えない」のだ。「でも高い三線だからいいとは限らないわけ。自分自身の感覚に合うのであれば、安くても良い。気に入った三線は、何者にも勝る」。

ブランド価値としての三線
現在、定男は沖縄県三線製作事業協同組合が委託する「県産三線普及ブランド化委員会」の委員を務めている。
委員会の目的は「三線職人だけでなく、多くの愛好家や演奏団体・三線製作店や文化団体など、三線に関わる全ての方々と一丸となり、三線のブランド化に向けて取り組んでいく」ことだが、委員のお一人として、三線のブランド化についても聞いてみた。
「三線というのは、持っている人によって価値観が異なるものだと思っている。私のような実演家や三線の収集家もいる。その中で、三線のブランド化を図るというのは、まずは国のお墨付きをもらうこと。名工や国の文化財指定を実現することから始まるのでは。そのためには、組合が認定している印をつけるべきだし、ブランド品としての説明も必要。そして考えるべきなのは、どうして三線が国の文化財指定をされないかということ。三線というのは、ウチナーンチュの持つアイデンティティーの最前線にあるものだと私は思っている。ウチナーンチュの心の糧といってもいいんじゃないかな」。
実際、戦後の復興に三線が大きな力を発揮したのは誰でも知っている。
三線は「心と心を癒し、人の気持ちを優しくするもの。世の中を変えてしまう程の力があるのも三線。沖縄音楽は独特のウチナーンチュのリズムを表現している、私たちウチナーンチュのDNAそのものといってもいい」。
さらに、「私がこれまでお話をさせていただいた喜舎場永珣や山内盛彬、池宮喜輝、新屋敷幸繁、各先生たちの、生活の中にあったもの」だという。
定男の紡ぐ音楽
定男自身、唄を創る際には「古い唄のエキスを残しているし、古い唄が私の中で甦生して、それが新しい唄として生まれ出すものなんだよ。唄は形を変えていくもの。なくなっていくのは仕方がないけど、どこかで必ず甦生するものだと考えている。古謡を文化財に指定しても形が残るだけ。心は残っていない」とのこと。
その中で核となるのが三線ということになるのだと、お話を聴きながら思った。
それでは創作の際、三線を手にしているのかを聞くと、「作曲のときは、楽器の音色を極力排除したいと思っている。自然の中の音、風や波の音、葉擦れの音とかを聴いていると、それが音に結びついてくるわけ」。それはやはり、三線や他の楽器が常に頭の中にあるからだろう。
そして「唄は生きているもの。唄を歌うたびに違う。それは空気や風、そして唄う私自身の感情が異なっているからだろうね。三線の音色も、唄うたびに違うもの」。
音・曲・そして唄う人自身も、その環境や場所で違うものなのだろう。
しかし、三線そのものの魅力は変わることはない。
三線の持つ精神世界
インタビューも最後に近づいてきた。そこで、定男が持つ三線の世界観について尋ねてみた。
「三線というのは、弾く人のものであって、それぞれ価値観が違う。名器であろうがなかろうが、その人が大事にしているものであれば、それはいかなる名器にも勝るものだと思うよ。南米に行ったことがあるけど、そこで大事にされている三線は、とても大事で貴重なものだった。金銭的な価値観とは別の意味でね」。
それは、受け継いできた魂ともいえると思う。
「笠戸丸で移民として渡っていったウチナーンチュの三世でミヤシロさんという方と知り合ったけど、その方は、今でも一日・十五日には仏壇に手を合わせているって聞いた。おじいさんから受け継いできた三線も大事にしている。自分は三線を弾くことはできないけど、孫には習わせていると言っていたよ。三線がウチナーンチュとしての根っこになっているわけ。ウチナーンチュとしての魂を大事にしているんだね」。
三線そのものの価値ではない、三線の持ち主の思いという価値がそこにはあるんだということを実感した瞬間だった。
受け継いできた家宝の三線
知名家には家宝として大事にしている三線がある。由来を聞くと、「(琉球政府が認定した「組踊保持者」の)平良雄一さんから普久原朝喜さんが引き継ぎ、それが父の知名定繁に伝わって、私が譲り受けたわけ。南風原型でね。今でも大事にしている三線で、池宮喜輝の『三線宝鑑』にも掲載されている名器だよ」とのこと。インタビュー終了後に見せていただいたが、皮は破れているものの、棹は今でも光沢を放っており、名器と呼ぶにふさわしい三線であった。
「この三線は、大阪から沖縄に来るときでも大事にしていた三線で、それこそ我が家から一歩も出さない大事なもの。かつて三線収集家が、この三線のことを聞きつけて、是非譲ってくれと言ってきたけど、それでも手放すことはなかったよ。当時、私は借金を抱えていて、非常に厳しい時代だった。その人は2千万まで出そうと言ったけど、やっぱり売ることはできなかった。2千万円という金額は喉から手が出そうなくらい魅力的ではあったけどね」。その三線は定男にとってお金に変えられない価値を持つものだった。「最後には幾らだったら売るのかと聞かれて、一億でも売らないと言ったので、さすがにその方も手を引いた」のだという。「もし、借金返済のために売ったとしても、結局は買い戻したと思う。幾らかかってもいいから。だから私は、苦しくても売らなかったという誇りも、この三線には込められているわけ」。
今でも正月の時や自身のリサイタルなど、節目のときに弾く家宝の三線。
定男だけでなく、代々引き継ぎ、奏でてきた方々の想いも詰まっているように感じられた。

最後に
最後に、これだけは言っておきたいことを聞いた。
その言葉は、実演家として、音楽プロデューサーとして、そして音楽界の歴史を知る者としての定男の姿勢が感じられるものとなった。
それは、三線に対する思いであり、三線業界への提言ともなる内容であった。
あえて、箇条書きにして、結びとしたい。
「三線の型はいくつかあるけど、その型の検証をきちんと行うべき」
「職人さんたちの事績や系譜もきちんと調べて、明らかにすべき」
「それを確かな研究資料として残すべきである。それは今の人たちの責務だろう」
「三線の持つ音色はさまざま。それぞれ性格が違うといってもいい」
「新しい三線を手に取るときのワクワク感が楽しい。どんな音がするのかなってね」
「三線の楽しみ方は、いろいろある。その楽しみ方を自分自身のものとして、味わって欲しいし、それを探ってもらいたい」
(北中城村の自宅にて)
インタビュー:宮城一春
沖縄県三線製作事業協同組合
支援:公益財団法人沖縄県文化振興会