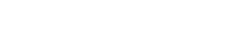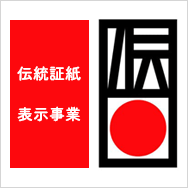三線作家
沖縄県工芸士
三線工房 響(ひびき) 代表
独学で学んできた。師匠はお客さん。
がっちりした体格から太く大きな声を出す譜久山勝氏(以下敬称略)。三線工房「響(ひびき)」の店内に響き渡るその声は、与那国島で鍛えられた。
「風が強くてね。新北風(みーにし)が吹く季節が過ぎると、海風のうなるような音がして、学校へ行く道でも同級生と大声で話さないと聞こえない。そんな環境だったので、いつの間にか声が大きくなった(笑)」
1949年に与那国で生まれ、高校進学のとき那覇に移り住む。オーダーメイドの紳士服店経営、掘削のボーリング調査の仕事にも就いた。ウタサー(※「ウタサー」とは歌三線を実演する人のこと)としても20代後半から八重山民謡を学び、1987年には石垣市主催の「とぅばらーま大会(石垣島開催)」で優勝。また、日本武道館で開催された「第10回日本民謡大賞」に沖縄県代表として出場、優秀賞を受賞している。そしてこの頃には、すでに三線づくりもスタートしていた。すべて独学、ゼロから学んだ。師匠はいない。

「30代半ばから、見よう見まねで三線づくりをはじめた。そりゃあ失敗もよくしたよ。で、どうして失敗したんだろうって考えながら、また製作をはじめる。その繰り返しだった。他の仕事もしたけどやはり三線づくりが自分に合っていたね。2年製作に打ち込んで、初めて友達が三線を購入してくれたときは嬉しかった。でも今思えば、友達は私を勇気づけるために無理して買ってくれた筈なんだ。ありがたいことだね」
教科書の存在しない三線づくりという世界では経験がすべてだ。製作した本数が自分の教科書として蓄積されていく。
実際の製作工程を通してさまざまな原木に触れ、各部位によって構成される全体のバランスで音色がどう変わるのかを自分の耳で確かめ、完成した三線をお客さんが構え、演奏する様子までイメージしながら、理想の音色をつくりだしていく。
「お客さんが師匠だと思っています。ひとりとして同じお客さんはいないでしょう。年齢も体格も声も、すべて違う。だから、毎回教わることがあるんだ」
ここから県内外へと巣立っていった三線は、ウタサーと出会い、個性あふれる音色を響かせることで、次の新しいお客さんを惹きつけてきた。譜久山の三線が欲しいと、わざわざ県外から工房へ訪れるファンも多い。譜久山勝作品としての三線の直線美、曲線美、角のシャープさといったアート性から、音色、存在感に至るまでの魅力が次々に新しいお客さんを惹きつけ、魅了してきたのだ。
イメージしながら三線をつくる。
三線づくりは手紙を書くことに似ていると、譜久山は言う。そこにはどのような思いがあるのだろう。
「相手をイメージしながら文章を綴るのが手紙でしょう。そうじゃないと、ひとりよがりな文面になってしまう。三線づくりも、お客さんをイメージしながらつくりたいんだ。できればお客さんと会って5分でも10分でもいいから話しをして、それから製作へと入っていきたいね」
ときどき、県外から訪れるお客さんに沖縄そばをつくることがある。わざわざ工房まで訪れてくれるお客さんへのおもてなしだ。ていねいに出汁をとり、麺の太さの好みまで訊いてからつくる。お客さんとのコミュニケーションを大切にしている姿勢が、こんなところからもうかがえる。
「そばづくりには自信があるよ(笑)。でも、遠方に住んでいてどうしても忙しくて工房に来られない人だっている。それでも私は少なくてもお客さんの顔を見てから三線づくりに入りたい。そんな人には、顔写真をメールで送ってくれないかってお願いをしたこともある。三線つくるのに顔写真なんて必要がありますかって、驚かれたけどね」
三線をつくって終わるのではなく、メンテナンスも積極的に行うため、お客さんとの付き合いがとても長く、リピーターも多い。何年も前に三線を購入したお客さんが訪れて、小学生になった子供のために一本オーダーするという、親子二世代にわたる付き合いもある。
また、2003年から石垣市主催「とぅばらーま大会」最優秀賞の受賞者への副賞として、毎年新作の三線を寄贈しつづけている。それまでの記念品は航空券や泡盛などが多かったため、カタチに残るものとして三線を寄贈することで八重山民謡の発展に貢献したいとの想いからだ。三線が長い歴史を刻んできたように、三線職人として深く、長く、人に愛される三線をつくりつづけたいと願っている。
「久々に元気そうにしているお客さんに会うと、三線も元気にしてるかぁー?って訊いてしまうんだ」と、表情をゆるめる。

削りに集中できるのは、真夜中。
周囲にサトウキビ畑が広がる八重瀬町の三線工房「響」、1991年に看板を掲げた工房内の作業場を見せてもらった。
希少価値の高い原木が並ぶなか、工具箱にはノミやヤスリなどが無造作に置かれ、木くずを吸い込む大型集塵機もある。とても広い作業場だ。
天の型をつくるために刃物を入れながら譜久山は言う。
「得意とする型? 与那城(通称:ユナー)、江戸与那城(通称:エドユナー)はよくオーダーをいただくね。シャープなラインを表現するように心がけている。棹材は、堅いだけじゃダメなんだ。堅くて弾力性のあるものがいい。削ると、粉々になるのではなく、カツオ節みたいにきれいにめくれるのがいい棹材の証拠。こうして刃物を入れはじめると、完成したときの音がイメージできる」と、徐々に表情が職人になっていく。
「失敗を恐れて、安価な雑木で製作の練習をする人は、職人としては伸びないよ。最初からいい材を使った人の方が成長も早い」
昼間から作業に入るが、譜久山がもっとも集中できるのは真夜中だ。そしてBGMはジャズ。
「ときに軽快に、ときにしっとりと聴かせるジャズは、おしゃれな気持ちにさせてくれる。伝統工芸品としてのアートな魅力を表現することも、三線づくりには欠かせないからね。だから、私のBGMはジャズなんだ」
休日になると、馴染みの店でウィスキーを飲む。泡盛を飲むこともあるが、どちらかというと洋酒好き。こんなところにも、おしゃれな一面を垣間見ることができる。
今夜も三線工房「響」には明かりが灯る。そこには、三線を構えて唄うお客さんの姿をイメージしながら、棹材を削っていく譜久山の姿がある。大きく厚みのある職人の手から、繊細でシャープなラインが描き出されようとしていた。

(高木 正人)
沖縄県三線製作事業協同組合
支援:沖縄県、公益財団法人沖縄県文化振興会