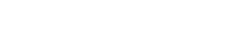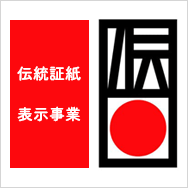仲嶺三線店 代表
沖縄県工芸士
三線づくりは、音づくり。
仲嶺盛文氏(以下敬称略)は三線について語るとき、三線そのものをひとつの人格のように表現する。得意とする真壁型について語り出したときも、まるで女性の人柄に置き換えるように語ってくれた。
「強がりすぎず、尖りすぎない、優しい美しさがそこにはある。そんなエレガントな音色が、真壁型の魅力だね」
50年にわたってベストの仕事をしてきた。それでも、「満足できたのものはまだない」。今でも向上心をもって仕事をしている。
高校時代、12歳年上の兄(仲嶺盛英)の元で三線づくりをはじめた仲嶺盛文。チーガ(胴)によって隠れてしまう部位、チーガタムチ(心)を繰り返しつくりながら、腕を磨いた。
ギターが共鳴体によって音を響かせるように、三線はこのチーガタムチが振動を感知し、棹を通ってチラ(天)へと振動を運んでいく。
「三線には7つの型があるけど、チラは音色をつくる重要な部位です。かつての名工たちの名によって7つの型に分けられているというより、音の違いを示したものだと考えた方がいい」

三線づくりは、音づくりー。この哲学こそが仲嶺の三線づくりの中心にある。だからいつもお客さんの声質や歌い方を聴き、唄者としての個性を際立たせるように、三線をつくる。
「たとえば硬い声の人には柔らかい音の、柔らかい声の人には硬い音の三線。唄者の個性に同化させるのではなく、少しだけ対比させることを心がけています」
すべての工程に意味がある。
原木にノミを入れた瞬間から、一気にカタチへと仕上げていくのが仲嶺の仕事スタイルだ。
「イメージが逃げてしまわないうちに、8割ぐらいまでをつくってしまうことにしている。その数日間は、集中することにしているよ。集中するためには健全な精神と健康な身体でなければならないでしょう。だから、酒はもうやめたんだ」と、職人魂をのぞかせる。
仲嶺は1990年代初頭に、三線製作の世界にも技術革新がおきたと振り返る。それまで手づくりだった工程に新しい設備が導入され、より精巧な三線を作ることができるようになった。

三線のメカニズムを知り尽くしていた仲嶺にとって、大きな刺激になったと同時に、三線文化がさらに開花し、成長していく予感に心躍らせたのが40代のころ。
すでに職人として独立を果たしている息子の仲嶺 幹(なかみね みき)を育成。技術の伝承にも、力を入れている。
「技は見て盗め? それは違う」と、育成論を語る。「すべての工程に意味があることを、きちんと一つひとつ説明する責任が職人にはある。それが技術の伝承になると思っているんだ」
たとえばおいしい料理をつくるとき、塩を入れるのはこの工程で、火にかけるのはこのタイミングでなければならない理由があるのと同様、三線づくりの工程すべてに道筋があり、そこには意味がある。
それらの説明責任を果たしていくのも、自分の役割だと感じているのだ。
「20才までは勉強、40才までに専門の仕事をもつ。60才までに華を咲かせ、それ以降は後継者を育てる。それが私の人生論なんだ」
つくり手は、外科医のようなもの。
真剣な話の途中に、すこしだけ冗談をはさみ、場をやわらげようと気遣う。そんなとき、鋭い職人のまなざしから一転、柔らかい表情へと変わる。
「人は、自分の人格以上のものをつくることはできないと思うんだ。だから私も、人格をもっと高めないといけないね」と謙虚さを忘れない。
工房内には、カミゲン、八重山黒木、白太の入った材など、さまざまな原木が運ばれてくる。そしてときどき珍しい材を仕入れることもある。
「八重山あたりで築何十年も経過し、ようやく家屋としての生涯を終えて、解体された梁や柱が運ばれて来ることもあります。その中には、目を見張るようなすばらしい黒木もある」
何世代もの暮らしを支えてきた家屋の材に、新しく三線という生命を吹き込む。
「三線というのは、木の最期の命だと思う。三線に生まれ変わることで、再び何世代もの人々に愛される命になっていくんだ。ロマンがあるよね。でもだからこそ、いい加減な仕事はできない。手を抜いたりしたら、バチが当たるはずさ」
三線のメンテナンスも大切にしている。唄者たちとの長年のつきあいの中で、三線の「健康」状態をいつも診断する。そんなときは、外科医のようなまなざしになる。

「この部位がケガをした。これなら簡単な手術で完治するよとか。この症状は重いから、新しい三線をつくった方がいいよとか。的確なアドバイスをするのも、つくり手の仕事だね」
三線に人格を重ね合わせ、その命を守りつづけようとする仲嶺の元に、多くの唄者、奏者たちが集まってくる。
(高木正人)
沖縄県三線製作事業協同組合
支援:沖縄県、公益財団法人沖縄県文化振興会